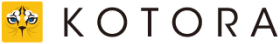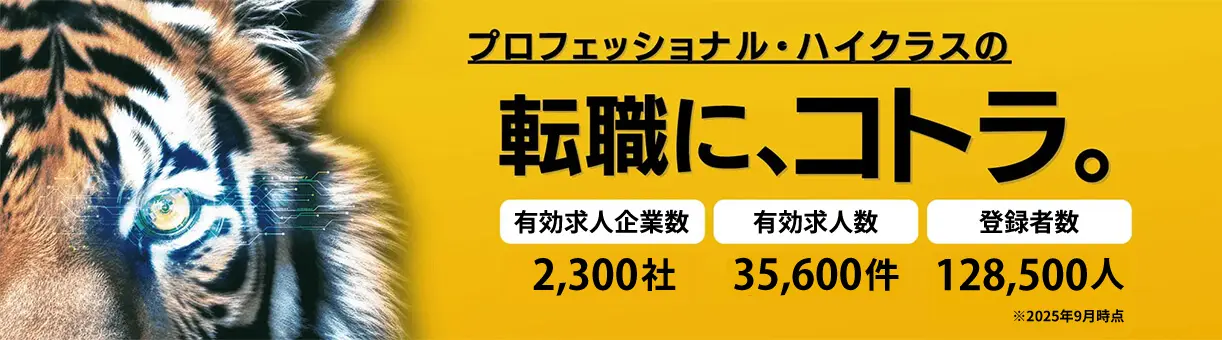オルツ、上場から10カ月で破綻 “単純すぎた粉飾”と崩れた信頼の連鎖

2024年10月に東京証券取引所グロース市場へ上場し、「大型ベンチャー」ともてはやされた人工知能(AI)開発企業のオルツが、2025年7月30日付で東京地裁に民事再生法の適用を申請した。同日、東証は8月31日付で同社株式を上場廃止とすることを決定した。市場に鳴り響いた鐘からわずか10カ月での急転だった。
単純な構図の不正会計
破綻の発端は、主力サービス「AI GIJIROKU(AI議事録)」の売上をめぐる過大計上疑惑だった。2025年7月29日に公表された第三者委員会の調査報告書により、不正の構図は極めて単純なものであったことが明らかになった。
オルツは、議事録サービスを自社サイトおよび代理店経由で販売しており、なかでも「スーパーパートナー(SP)」と呼ばれる販売代理店にライセンスを一括販売した時点で売上を計上していた。しかし、実際にはSPにライセンスが発行された形跡はなく、広告費や研究開発費の名目で第三者に支払われた資金が、SPに還流していた。この資金の流れは実質的に「循環取引」と結論づけられている。
この手法は、創業者で元CEOの米倉千貴氏の主導で2021年6月頃から行われており、2022年12月期の売上高の91.3%、翌期も91.0%がこのスキームによって水増しされていた。2021年から2024年までの累計で、過大計上された売上高は約119億円にのぼる。
公表と実態の乖離
同社の有価証券報告書では、2024年12月期末時点での「AI GIJIROKU」有料アカウント数は2万8699件と記載されていた。しかし、第三者委の報告によれば、2025年7月時点での実際の有料アカウント数はわずか5170件、そのうち直近でアクセス実績があったのは2236件に過ぎなかった。
見逃された「疑念」
監査法人やベンチャーキャピタル(VC)、証券会社、そして東京証券取引所は、この単純な構図に気付くことができなかった。
同社はもともと別の監査法人によって監査されていたが、2021年12月期の監査が完了せず、2022年10月に契約を解消。以降は横浜拠点のシドーが監査を担った。引き継ぎ時に「循環取引の可能性」が申し送り事項として伝えられていたにもかかわらず、提出された資料等により、不正の可能性はないと判断された。
この対応に対し、企業会計に詳しい青山学院大学名誉教授の八田進二氏は、「AI GIJIROKUのような無形アカウントであっても、存在確認は不可能ではない」と監査の甘さを指摘する。
一方、オルツは資金調達時にVCや主幹事証券、大和証券、東証に対しても、実態と異なるアカウント数や広告費の使途、監査法人交代の理由などを説明していた。虚偽の説明により、投資判断や審査の目が曇った可能性は否定できない。
東証の山道裕己CEOは、7月30日の定例会見で「上層部が結託して意図的にだまそうとした場合、監査法人ですら見抜けない」と述べ、審査の妥当性には問題がないとの見解を示した。
CFOの「沈黙」と共犯関係
さらに不正の構図を複雑化させたのは、2021年10月に入社したCFOの日置友輔氏の存在だ。第三者委の報告書によれば、同氏は入社直後にスキームの存在を知らされ、異議を唱えることなくこれを受け入れていたという。市場関係者の一人は、「大手証券出身者であれば、本来こうしたスキームに同意すること自体が異例」と驚きを示す。
こうした共犯関係がスキームの継続を容易にし、不正発覚の遅れにつながったとみられている。
投資家保護の視点から
今回の事案は、2009年にIPOから半年で上場廃止となった半導体メーカー・エフオーアイの粉飾事件を想起させる。市場の健全性を維持するうえで、監査法人、VC、証券会社、そして取引所が果たすべき役割と責任が、あらためて問われている。
東証の山道CEOは「こういう人たちは常に出てくる」と語るが、被害を受けたのは一般投資家である。関係者それぞれが、どこに“妄信”があったのか、冷静な自己検証が求められる。
引用元記事:https://news.livedoor.com/article/detail/29299435/